2017年09月19日 朝のいい加減な習慣
|
モーニングコーヒーに始まり、朝刊二紙のチェックは定番だ。テレビ体操、仏壇前の読経は努力目標、スマホによる情報チェックは最近始めた。日経、ヤフー、NHKなどでネット記事を読んだり映像を確認したりしている。趣味で続けている美術関連記事の切り抜きはすでに3年目となった。 朝食後に免疫力を強化すると信じて蜂蜜を舐め、血圧降下剤とビタミン補助剤を飲むことはしっかり習慣化した。問題は身体を動かすことが少ないことである。新陳代謝が落ちる年代にあっては散歩が良いとは思うのだが未だ実現には至っていない。もっとも、なんでもやり過ぎる性格なので、先日も筋トレして腰痛に襲われた。いい加減とは難しいのである。 |
2017年09月12日 シンガポール見聞録
|
高所恐怖所の身には危険な視察場所が多くあるとガイドブックで事前に把握していた。しかし、大観覧車はパスして難を逃れたものの、マリーナベイ・サンズの57階の展望台では足が竦み、セントーサ島に行くゴンドラでは地上60mの地点で目を閉じつつも全身から冷や汗が吹き出た。 現地ツアーガイドの話で興味深い点を少し紹介する。建国52年で国民の平均月収は30~35万円。但し物価は高く、例えば輸入車は関税100%、車所有権は入札制で約400万円(しかも10年間の期限付き)もする。大臣の月収が2500万円ぐらいなのは、汚職防止のためとか。中国やマレーシアのごとき汚職が多い国は見習うべきだろう。世界トップクラスのコンテナ港にはガントリークレーンが文字通り林立し、9月13日からはF1レースが開催されるなど活気溢れる様には終始圧倒されたのである。 |
2017年09月04日 ジョン・レノン・ミュージアムで
|
そこで偶然見つけたのが、再開発ビルの一角にある期間限定(2000年から2010年まで)でオープンしている「ジョン・レノン・ミュージアム」である。自由時間があったので、迷わずに直行して入館したが、さすがに見応えがあった。 一番感心した展示物は、ホテルのメモ紙に書かれたイマジンの歌詞である。世界の人々に感動を与えた歌が粗末な一枚のメモ書きから生まれたのだ。さらにオノヨーコさんの作品に、ハシゴを登って虫眼鏡で天井の見るというものがあった。興味津々に眺めた天井には、「yes 」の小さな文字。それがオノヨーコさんの「天井の絵/イエス・ペインティング」という作品であることは最近知った。ふと、全ての依頼にyesと答えることで人生が変わったというアメリカ女性のことを思い出した。 |
 良い習慣を身に付けたいと思っているが、努力目標で終わっているものが多い。最近は朝目覚めるのが早くなっているので、朝の使い方に工夫が必要だ。
良い習慣を身に付けたいと思っているが、努力目標で終わっているものが多い。最近は朝目覚めるのが早くなっているので、朝の使い方に工夫が必要だ。  久しぶりにシンガポール視察旅行に参加した。福岡空港発のシンガポールエアラインは客室乗務員のユニフォームが懐かしかった。約6時間の飛行時間で時差は-1時間。気温は30度を越え、湿度も高く、滞在中常に汗を掻き続けた。
久しぶりにシンガポール視察旅行に参加した。福岡空港発のシンガポールエアラインは客室乗務員のユニフォームが懐かしかった。約6時間の飛行時間で時差は-1時間。気温は30度を越え、湿度も高く、滞在中常に汗を掻き続けた。 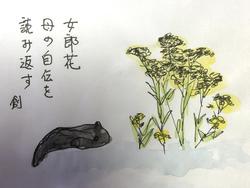 オノヨーコさんの「フャミリーヒストリー」というNHK番組を見て、突然思い出したことがある。それは2001年にさいたま市が誕生した際、駅前再開発の視察に同市を訪れた時のことであった。同市は浦和市、大宮市、与野市が合併してできた市であり、いち早く政令指定都市になるなど熊本市にとっては参考にすべき点が多かった。広く奇麗なペディストリアン・デッキ(歩行者回廊)が設置してあるなど、確かに立派な駅前再開発ぶりであった。
オノヨーコさんの「フャミリーヒストリー」というNHK番組を見て、突然思い出したことがある。それは2001年にさいたま市が誕生した際、駅前再開発の視察に同市を訪れた時のことであった。同市は浦和市、大宮市、与野市が合併してできた市であり、いち早く政令指定都市になるなど熊本市にとっては参考にすべき点が多かった。広く奇麗なペディストリアン・デッキ(歩行者回廊)が設置してあるなど、確かに立派な駅前再開発ぶりであった。