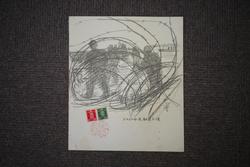2014年10月14日 社員食堂と花嫁修業
|
さて、別のNHK番組で面白いのは、全国各地で繰り広げられる中食の様子を取材した「サラメシ」です。中井貴一さんが素っ頓狂な声で解説するのもおかしいのですが、まさに地域ならでは中食風景や各人それぞれのこだわり弁当などがあり、見る人を惹き付ける番組です。我が社の場合は、コンビニ弁当で済ます人とお母さん又は自分で作った弁当を持参する人が半々といったところです。最近のコンビニ弁当の進化を見ていると、簡便で美味しい弁当がすぐに買える現代社会では、若者が焦って結婚しようとは考えないはずだと納得したりします。
|
2014年10月06日 マッサンの余市
|
|
2014年10月01日 シンガポール陥落のあれこれ
|
そういえば、先日元国会議員が自ら所有しているという東条英機氏の色紙の話を興味深く聞かせてもらいました。それは、戦争犯罪を追求された同氏が、戦後開かれた国際裁判中に親しい人に送った辞世の句というものです。それは、「絵踏みして 生きるもくやしき老桜 散ると知れや 風さそうまま」というものです。
|