2026年01月13日 他者との関係
|
会場で一つ気づいたことがあった。それは小学4年生まではその作品の大半が人物か動物を描いているのに対して、小学5年生より上になると大半の作品が静物か風景の絵になり、人物や動物の姿が忽然と姿を消すのである。これは学校側の指導によるものなのか、学年が上がるに伴い子供らの人や動物に対する関心がなくなるからなのかとても気になった。というのも他者との関係性を良きものにすることが人間社会では大切だからである。若い時から孤独になって欲しくはないと思った。 |
2026年01月07日 根こそぎ
|
雑草取りにコツがあるかどうか知らないが、植えている植物ができるだけ重ならないように不要なものを除去するよう心掛けている。作業しながらも視点を変えるために、遠く離れて確認したりと意外と繊細な作業を強いられる。もっとも昭和天皇か牧野富三郎博士が「世の中に雑草という植物などない」と言われたことを思い出しながらではあるのだが。 今回発見したのは雑草と目したカタバミの根の深さだ。再生力の強いカタバミは地面に出ている葉を取っただけではすぐにまた葉を再生させる。従って深く土を掘り根こそぎ除去するのだが、その根の立派さに「天晴れ」と思った。織田信長は宿敵を亡ぼすにあたり、「根絶やしにしろ」と命じたのは二度と子孫係累が再生しないようにとした訳である。そのことをカタバミの根を見ながらなるほどと納得した。「根こそぎ」と「臭いものにふた」とは対極にある考えだ。 |
2025年12月22日 今年の冬は
|
今年の冬は例年に比べても暖かい。猛暑、酷暑の夏から厳しい残暑が続き、急に気温が下がった時は秋をパスして一挙に冬になった気分になったほどだ。その頃は体調管理が大変だったことを思い出す。そして冬至の今、この暖かさはやっぱり地球温暖化の影響かと不安に襲われるのである。 庭の紅葉も今年はなかなか色づかないと思っている内に枯葉になって散り始めた。なんとも風情のない秋だった。いやそもそも秋がない一年であったというべきかもしれない。とはいえ、庭にある2本の紅葉のうち1本だけはやっと紅葉し庭を彩ってくれたのは、春から枝の剪定にいそしんだ身にとっては季節の贈り物と思え内心嬉しかった。 |
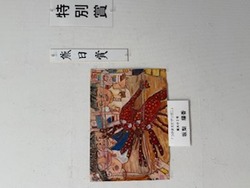 この週末、熊本県立美術館分館で開催されていた第79回熊日学童スケッチ展を観てきた。本当は他の会場の九州モダンアート展に出品されている知り合いの作品を観るのが目的だった。そのついでに学童スケッチ展に足を伸ばしたという訳である。
この週末、熊本県立美術館分館で開催されていた第79回熊日学童スケッチ展を観てきた。本当は他の会場の九州モダンアート展に出品されている知り合いの作品を観るのが目的だった。そのついでに学童スケッチ展に足を伸ばしたという訳である。 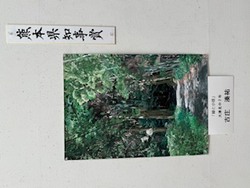 現代アートにとんでもない高値がつく現代、私にとってその真価を見極めるのは難しい。好きか嫌いかならば良いのだが、その価値を判断するなど到底できない。一方、学童の絵には難しい思想の痕跡など微塵もなく、ただ純粋な感受性だけが感じられて好ましかった。と同時に絵を描く上級生のテクニックには驚きを禁じ得なかった。
現代アートにとんでもない高値がつく現代、私にとってその真価を見極めるのは難しい。好きか嫌いかならば良いのだが、その価値を判断するなど到底できない。一方、学童の絵には難しい思想の痕跡など微塵もなく、ただ純粋な感受性だけが感じられて好ましかった。と同時に絵を描く上級生のテクニックには驚きを禁じ得なかった。  年末の大掃除では主に庭の雑草取りに時間を費やした。庭の手入れは一種の空間芸術に似ており、しかも植物は生物でもあるので愛情が欠かせない。その愛情を持ちながらも申し訳ない気持ちで雑草を抜くのである。もちろん庭仕事には失敗はつきもので、年末購入したシクラメン3鉢は液体肥料を薄めないまま施した結果全滅させた。
年末の大掃除では主に庭の雑草取りに時間を費やした。庭の手入れは一種の空間芸術に似ており、しかも植物は生物でもあるので愛情が欠かせない。その愛情を持ちながらも申し訳ない気持ちで雑草を抜くのである。もちろん庭仕事には失敗はつきもので、年末購入したシクラメン3鉢は液体肥料を薄めないまま施した結果全滅させた。  この1年を振り返ると、国内外で政治経済や自然災害などあらゆる分野で目を見張るような出来事が相次いだ。いずれメディアから年間10大ニュースとして発表されるだろうから、ここでは詳細には触れまい。ただ、年末恒例の今年の漢字に「熊」が選ばれたのには驚いた。熊の住んでいない九州にいると熊の出没はよそ事に思えるからである。九州人の願いは、熊が関門海峡を泳いで九州に来ないことなのである。
この1年を振り返ると、国内外で政治経済や自然災害などあらゆる分野で目を見張るような出来事が相次いだ。いずれメディアから年間10大ニュースとして発表されるだろうから、ここでは詳細には触れまい。ただ、年末恒例の今年の漢字に「熊」が選ばれたのには驚いた。熊の住んでいない九州にいると熊の出没はよそ事に思えるからである。九州人の願いは、熊が関門海峡を泳いで九州に来ないことなのである。